こんにちは
2025年9月からUniversity of California San Diego(UCSD)に進学予定のTakuです。
私は中学生から英語を学び始め、中学2年生で英検2級、高校1年生で英検準1級に合格し、秋からアメリカ大学に進学予定です。
今回は、中学時代の英語学習の中でも「長文授業」について振り返っていきます。
※まだ前回(文法授業編)をご覧になっていない方は、ぜひこちらからご覧ください
文法と並ぶもう一つの柱「長文授業」
私の中学校では、英語の授業が大きく
- 文法(Grammar)
- 長文読解(Reading)
の2つに分かれており、前回は文法の授業について詳しく紹介しましたが、今回は「長文読解編」です。(文法の授業について読みたい方は前回の記事をご覧ください)
長文の授業
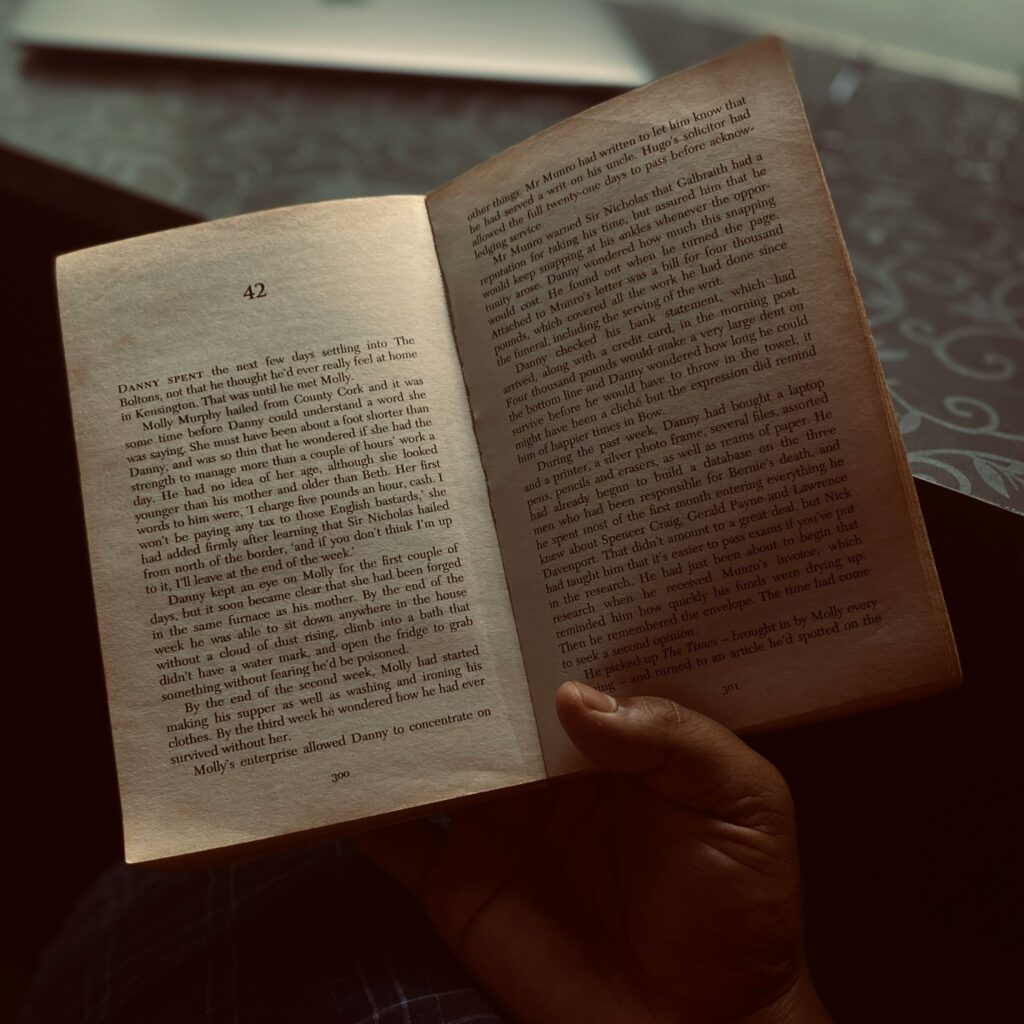
- 授業の流れと進め方
長文の授業も最初は英語に慣れることからスタート。
アルファベット(A B C D…)を音声にあわせて発音していくところから始まりました。
その後は、以下のような流れで進んでいきました:
授業では本文の毎回、1~2段落ずつ読み進めていき、じっくり丁寧に学んでいくスタイルでした。
- 新出単語の配布(リスト形式)
- 単語の音読練習
- ペアワーク(一人が新出英単語の問題をだし、日本語訳をもう一人が答える形式)
- 本文解説(先生が一文ずつ文法と単語を詳しく解説)
- 内容確認問題の演習
自分自身中高一貫校だったので、ほかの学校がどのような授業をしていたかはわかりませんがオーソドックスな授業なのではないかと思います。
- 文法との相乗効果で読みやすく
最初は長文を読むのがとても難しく感じていました。
でも、文法の授業が進むにつれて、文章の構造がわかるようになり、次第に「そんなに難しくないかも」と思えるようになっていきました。
それに加えて、この授業では新出単語の小テストもあり、テスト対策のために必死で単語を覚えるうちに、あまり多くはないですが自然と語彙力を増やしていきました。
※ちなみに私は、最初から単語帳でガンガン覚えていたわけではなく、授業やテスト対策を通して少しずつ覚えていっていました。
- 長文のテスト対策
中間・期末テストでは、授業で扱った長文から
- 穴埋め問題
- 語順並びかえ問題
がよく出題されていました。
私はその対策として、長文を何度も音読していました。音読することで自然に頭に文が入り、テストも高得点が取れました。
音読に加え、
- オーバーラッピング(音声に合わせて一緒に読む)
- シャドーイング(音声を聞いてすぐ後を追って読む)
こうした練習を通して、ただ読むだけでなく音声を使いながら声にだすようになり、文の構造や表現がより自然に身についたと思います。
何度も書いていますが、声に出す習慣の大切さを本当に実感しています。
- 追記 基礎英語について
もう一つ触れておきたいのが、「基礎英語」の存在です。
中学校から「毎日基礎英語を聞くように」と言われており、実際に毎日聞いていました。
定期テストでも数問、その内容が出題されていました。
当時、まだ文法の「ぶ」の字もわからない状態で聞くのは正直きつかったです…。
でも、続けていくうちに少しずつ英語に対する抵抗感が薄れていったのを感じました。
(英語力そのものが上がったかは微妙ですが、「英語に慣れる」という意味ではとても良かったと思っています)(基礎英語で英語力が上がったいう人ももちろんいると思いますが、、)
まとめ
ということで、今回は中学時代の英語授業のうち「長文読解」について書いてみました。文法、長文読解の授業はどちらも中学三年間ほとんど同じ形式で進みました。
次回は、いよいよ「英検4級」に向けた挑戦について書いていこうと思います!
また読んでいただけたら嬉しいです!




コメント